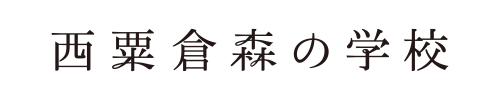木材工場で発生する樹皮とおが粉をいちご栽培に活用 オリジナル樹皮培地で循環型農業を実現する
2020年から西粟倉・森の学校はいちご栽培に取り組んでいます。
今回は私たちのいちご栽培の特徴でもある、樹皮培土について記事を書きました。
木材加工工程で発生する木材加工クズ・おが粉や有効活用されにくい樹皮を混合したオリジナル培土です。
いちご栽培を通して、今まで有効利用されていなかった樹皮やおが粉が美味しいいちごを育てるための培地になることが非常に面白いと感じています。
木材加工で必ず発生する樹皮やおが粉をいちご栽培に活用する

私たちは地域で伐り出される杉や桧を原材料に、住宅用内装材やDIY向け製品を製造しています。
木材加工工程では木材加工クズ・おが粉や製品には利用しない樹皮が必ず発生します。
おが粉は燃料用材として燃やされたりや家畜の敷料(牛や豚の寝床)として使われるため、西粟倉・森の学校は専門業者に販売しています。
おが粉はかつて、駅のホームで酔っ払ったおじさんが吐いた嘔吐物に振りかけ水分を吸着して掃除しやすくするために使われていたこともあるそうです。
樹皮もまた燃料用材に活用されますが、土や石が付着することが多く、焼却時の妨げになってしまうこともあり、あまり有効活用する方法がありません。
しかし、かつては樹皮は屋根や壁の下地材に使われることも多く、山師の副業として杉皮生産が重要な位置づけであったこともあるそうです。
私たちは地域資源の価値を高め切るモノづくりを目指しています。
しかし、木材製品を製造するために丸太を加工すればするほど発生するおが粉や樹皮は良い活用方法を見つけきれないでいました。
今回、西粟倉・森の学校の新たな取り組みとして観光型いちご農園を始めるにあたり、材木屋が育てるいちごらしさとは何だろう?と考えた時にたどり着いたのが樹皮培土でした。
いちご栽培には土は使わずヤシ殻が使われる?

いちご栽培には大きく分けて土耕栽培と高設栽培という方法があります。
土耕栽培は土に畝を立て、畝にいちごの苗を植える栽培方法です。畑で育てる野菜と同じです。
一方、高設栽培は直管パイプなどで架台ベッドを組み、培地を入れ、いちごの苗を植える栽培方法です。
高設栽培は屈まずに作業ができるため、作業性が高いメリットがある反面、設備コストが高いデメリットがあります。
私たち西粟倉・森の学校では、観光型いちご農園としてお客さまが摘み取りしやすい高設栽培を採用しています。
そして、農業は土づくりが命と言われますが、高設栽培においては土が使われない場合もあります。
ヤシの木の実の繊維・ヤシ殻や鉱物繊維・ロックウールで代替されることがあります。

- ヤシ殻 スリランカやインドネシアなど、東南アジアのヤシ殻を細かく砕いて培地にしたもの。気相率が高く安価なため、近年普及しつつあります。乾燥・圧縮させてブロック状にし、船で輸送されます。
- ロックウール 天然岩石を原料として、高温で溶融して繊維状にした鉱物繊維です。気相率が高く、かつ肥料の吸着性がないため、養水分コントロールがしやすいのが特徴です。産業廃棄物となるため廃棄コストが掛かってしまうことがデメリットです。私の前職トマト栽培法人ではロックウールでトマトを栽培をしていましたが、栽培に使いやすい反面、大量に発生する廃棄物を目の当たりにし戸惑うこともありました。
西粟倉・森の学校では、地域資源を循環させる農業を実現するため、樹皮培地を使用しています。
木材加工工程で発生する木材加工クズ・おが粉や活用されにくい樹皮を混合して利用しています。
栃木県内の木材開発協同組合が製造するクリプトモスという樹皮培地が販売・利用されている事例もあり、樹皮の特性を調べ、自社の木材加工工場で発生するおが粉と樹皮を混合したオリジナル樹皮培地でいちご栽培に取り組んでいます。
いちご栽培を通して今まで有効利用されていなかった樹皮やおが粉が美味しいいちごを育てるための培地になることが非常に面白いと感じています。
いちご栽培に適した培地特性とは?
いちごの栽培に適した培地とはどんな要素が必要なのでしょうか?
培地に求められる特性には、以下の3点があります。
- 培地の物理性
- 培地の化学性
- 培地の生物性
1つずつ解説していきます。
培地の物理性
まずは物理性です。
- 保水性と排水性の両面を持ち合わせている
- 均一性があり、ばらつきが少ない。
- 長期に渡り、物理的変化が少なく安定している
水が溜め込みすぎても、すぐに流れてしまっても根が水を吸い上げることができません。
培地が全体で均一でないと栽培する場所によってばらつきが発生してしまいます。
培地によっては複数年使い続けるものもあるので数年単位で物理的変化が少ないものが好まれます。
培地の化学性
次は化学性です。
- 肥料(無機塩類)の吸着が少ない。
有機培地には肥料の吸着力が高いものがあります。培地の肥料吸着力が高過ぎると根からの肥料分の吸収を阻害し、欠乏症状を引き起こす可能性があります。
しかし、適度な吸着力は肥料分を保持する機能を持ち必要分を根へと送る良い緩衝機能になります。吸着力が極端に高いものは、定植前に肥料分で満たし、十分に吸着させてから使用することで、欠乏症状を起こさないように栽培することができます。 - タンニンやフェノール類を含まない
タンニンやフェノール類は植物の生育阻害となるため、これらを含まない培地を選定します。また、それらが含まれているものは流亡処理を行ってから使用します。
美味しいいちごを育てるための培地であるはずなのに、その培地が肥料を過剰に吸着してしまっては苗に栄養が届かなくなってしまいます。
培地の生物性
最後に生物性です。
土壌病害の原因となる菌が少ない。
いちごの2大病害である萎黄病(いおうびょう)と炭疽病(たんそびょう)はどちらも土壌菌から発病する病害です。
・萎黄病の原因となる菌 … フザリウム(Fusarium)
・炭疽病の原因となる菌 … アキュテイタム(Acutatum)
このような病気の原因となる菌が少ないことが重要です。
いちごの健康を脅かす菌が繁殖しやすい培地であってはいけないということですね。
樹皮培地の特性といちごとの相性

私たちが利用する樹皮培地について説明します。
樹皮培地とは、木の皮(大半が杉や桧)を細かく砕き、混合・加工した培地です。
特徴は以下の通りです。
- 気相率が高い。
- 微生物分解を受けないため腐食しづらい。
- スギ、ヒノキの樹皮には抗菌物質が含まれており、土壌伝染病害を抑制する効果もある。
- 撥水性(水をはじく性質)が高く、水分保持が難しい。
- 肥料吸着力が高く、(特に窒素)使用前には培地に肥料を十分に吸着させる必要がある。
- 樹皮中にタンニンを含むため、使用時は鉄処理が必要となる。
いちごは、特に根域の酸素要求量が多いため、気相率が高く排水性が良い培地を好みます。
このため、樹皮培地の特性によく適した作物であると言えます。
その反面、水分保持力が少ないため、培地を乾かしすぎないような、より厳密な潅水管理が求められます。
また、場合によってはパーライト等の保水性が良い培地を30%程度混合して、保水性を高めることも重要です。
これらの特徴を踏まえ、私たちは樹皮をメインとしながらおが粉やパーライト等を適度に混合し適切な樹皮培地の研究に取り組んでいます。
また、適切なタンニン処理の方法や、肥料の吸着処理など、いちごの生育を阻害しないような方法についても研究を進めています。
タンニン処理で樹皮培地を仕上げる
杉や桧の培地を使う際のデメリットは、タンニンが多く含まれる点です。
タンニン(フェノール性の水酸基をもつ物質)はいちごの生育を阻害し、対照区と比較して5%程度収量が下がるという研究があります。
新しい樹皮を使用する際は、タンニン処理を行う必要があります。
タンニン処理は、鉄を含んだ液体に漬け込むことで、タンニンがタンニン鉄になり生育阻害しない物質になります。具体的には、市販の硫酸鉄で数時間漬け込めば十分効果を発揮します。
また、地面において雨ざらしで1年程度置いておくだけでもタンニンが流亡し、タンニンの含有量が下がり問題なく使用することもできます。
ちなみに、鉄クギや金属小物などを木材の表面に置いておくと、黒色に変色する場合があります。
これは、鉄や銅の金属イオンと木材中に含まれるタンニンが水分を介して反応し、化合物を生成するためです。
湿気が多い場所で木材の上に金属を長時間置く際は気をつけてくださいね。
樹皮とおが粉を活用した樹皮培地のまとめ

樹皮とおが粉を活用した樹皮培土についてまとめると以下です。
- 樹皮の特性を知り適切な工程で使用することで本来捨てていたモノがいちご生産で有効に利用できる
- 樹皮培地といちごの相性は良い。西粟倉・森の学校は樹皮培地で美味しいいちごづくりに取り組む
樹皮やいちごの特性を知った上で食べてみるいちごはまた違った味に感じるかもしれません。
私たちは美味しいいちごをつくるだけではなく、その生産背景も知っていただきたいと考えています。
ゆくゆくは、ご家庭でも簡単に育てられるいちごの苗と樹皮培地、木製プランターのDIYキットやワークショップなどにも取り組んでみたいです。